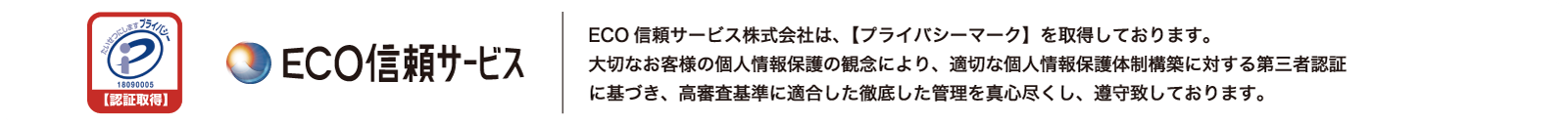
2023年9月23日
東京都市大学(東京都世田谷区)は9月19日、エネルギー変換効率が30%に迫る、曲げられる「ペロブスカイト/シリコンタンデム太陽電池」の作製技術を開発したと発表した。
今回開発した技術は、ボトムセルであるシリコンヘテロ接合太陽電池のシリコンウエハー厚を83マイクロメートル程度まで薄くするもの。この薄型シリコン太陽電池の上に、ペロブスカイト太陽電池を積層化して軽量・フレキシブルなタンデム型太陽電池を作製することに成功した。
記事内容へ
2023年9月22日
中越パルプ工業(富山県高岡市)と丸紅(東京都千代田区)は9月19日、中越パルプが製造するACCセルロースナノファイバー(CNF)を用いた、植物向けの新たな物理的防除資材「nanoforest-S」の普及拡大に関する取り組みが、農林水産省の「みどりの食料システム戦略に基づく基盤確立事業実施計画」に認定されたと発表した。
化学農薬の使用低減に寄与
同防除資材は、CNFを用いた新しい農業資材。植物に散布することで、資材に含まれる微細繊維が葉面を覆い、病原菌の侵入を物理的に防ぎ、化学農薬の使用低減が期待できる。
記事内容へ